
中長期での資産形成に、投資信託を活用している人が増えています。しかし、誰もが順調に資産を増やせているわけではありません。人気のあるテーマ型投信を高値づかみしてしまったり、相場の大幅な下落時に慌てて投げ売りしてしまった経験がある人は少なくないでしょう。投資信託のファンドマネジャーの経験もある、東海東京調査センター投資調査部の中村貴司さんが勧めるのは、投資信託での資産形成に「行動ファイナンス」の考え方や「テクニカル分析」を取り入れることです。
■投資信託での資産形成は、ファンダメンタルズに基づく判断だけでは不十分
最初に、私自身の苦い経験をお話しましょう。 私はかつて、証券会社で投資信託のセールスに携わっていました。当時は90年代後半から続くITバブルで、「ITが世界を変える」「ファンダメンタルズがいいから中長期的にも株価は上がっていくだろう」という認識が一般的でした。業績がよく、株価もどんどん上がっていたことから、IT関連に投資する投資信託を買いたいと考える個人投資家の方たちは多く、実際に非常によく売れました。
私はかつて、証券会社で投資信託のセールスに携わっていました。当時は90年代後半から続くITバブルで、「ITが世界を変える」「ファンダメンタルズがいいから中長期的にも株価は上がっていくだろう」という認識が一般的でした。業績がよく、株価もどんどん上がっていたことから、IT関連に投資する投資信託を買いたいと考える個人投資家の方たちは多く、実際に非常によく売れました。
しかし、ご存じのとおり、その後ITバブルは崩壊。購入のタイミングによっては高値づかみとなり、一部の顧客の方には損をさせてしまう結果になりました。この失敗から、中長期が前提の投資信託による資産形成であっても、ファンダメンタルズ分析に基づく投資判断だけでは不十分だと気づきました。その後、金融業界で多くの経験を通して学んだことが、今回お話したい内容となります。
ところで、ITバブルのとき、私はどのような行動を取るべきだったでしょうか。まず言えるのは、「もっと時間分散をするべきだった」ということです。何回かに分けて購入してもらえれば、高値づかみのリスクを多少減らすことができました。たとえ顧客の方から「みんなが買っているから、私も今すぐ買いたい」と希望されても、少し待ってもらうべきでした。また、高値圏かどうかを見極めてアドバイスする行動も必要だったと考えます。そのためには、ファンダメンタルズ分析だけでは不十分で、テクニカル指標を使った分析も重要です。
そして、さらに大切なことは、時間分散をする、焦って買おうとしない、高値圏かどうかを見極めるといったさまざまな事柄を、単に頭で理解するだけでなく、実際に行動に移すことです。そこで重要となってくるのが、投資家のメンタルのコントロールであったり、実際に投資行動へと促す「行動コーチング」なのです。日本にはまだほとんど入ってきていませんが、米国ではこうした「投資行動のコーチング」が重要視されるようになってきています。
■市場がファンダメンタルズ分析通りに動かない理由とは
ここで、「ファンダメンタルズ分析」について、改めてその理論を簡単に説明しておきましょう。ファンダメンタルズ分析とは、マクロの経済動向や企業の業績動向などを予測した上で、株価の理論価値(=ファンダメンタルズ価値)を計算して投資判断を行なう手法のことです。
ファンダメンタルズ分析がすべてであれば、株価は常にフェアバリューで推移するはずです。仮に、フェアバリューを超えて上昇した場合には速やかに元の水準に回帰するし、大幅に下落した場合も同様に元の水準に収れんしていくと考えられます。なぜなら、ファンダメンタルズ分析の考え方では市場は常に効率的で、投資家は常に合理的とされるからです。
けれども、実際の市場はどうでしょうか。フェアバリューを超えても元に戻るどころかさらに上昇したり、「○○バブル」と言われるような相場では関連する銘柄までどんどん上がったりということがたびたび起こります。また、リーマン・ショックのような局面では、理論価値にかかわらずあらゆる銘柄が売られてしまいます。なぜ、市場ではファンダメンタルズ分析では起きるはずのないことが頻繁に起きてしまうのでしょうか?
その回答の一つと言えるのが、ファイナンス分野に心理学の概念を取り入れた「行動ファイナンス理論」です。実は、行動ファイナンス理論は、実際の市場での現実と理論のギャップを埋めるために、伝統的なファンダメンタルズ分析とは対立する概念として登場しました。行動ファイナンス理論では、市場は非効率と説明されています。また株価は、投資家の感情やバイアス(先入観や根拠のない思い込み)に左右され、合理的とは言えない意思決定によって、適正価格を逸脱したモメンタムが起きたりバブルが生じるとされているのです。
■行動ファイナンスから見た、投資家にありがちな「バイアス」の例
では、市場や株価に影響を与える投資家の「バイアス」には、どのようなものがあるでしょうか。いくつか具体的に紹介します。
まずは「横並び行動」です。たとえば、「みんなが買っているから、自分も遅れずに同じものを買っておこう」といった投資行動のことです。多くの投資家がこの「横並び行動」を取ると、トレンドが形成されたり、さらにはバブルの形成やバブル崩壊につながる可能性があります。
また、「自信過剰」も行動ファイナンスにおける代表的なバイアスです。投資で上手く利益が得られると自分を過信して、ポートフォリオを考えずに過剰なリスクを取ってしまうような投資行動です。具体的な例としては、市場の暴落で損をした人は、しばらく暴落に対して極端に弱気になり、リスク・リターンに基づく投資ができなくなったり、逆に暴騰で儲けた人はその後も暴騰相場に極端に強気な行動を取るといったことです。
さらに、もう一つ挙げておきましょう。老後資金と教育資金と余暇資金、あるいはコアとサテライトのように、資金を分けて管理している人が陥りやすいバイアスが「メンタルアカウント(心の会計)」です。資金を分けていることを理由に、一部についてだけはハイリスク投資を許容しますが、実はトータルで見てもリスクを取り過ぎてしまっているという投資行動です。
冒頭で触れたようなITバブルやバブル崩壊の背景にも、こうしたバイアスによる投資行動が関わっています。行動ファイナンス理論を念頭に置いた株価推移は、ファンダメンタルズ分析による株価推移のイメージとは異なり、フェアバリューを超えて上昇したり下落したときに、さらにその方向に加速して乖離する動きを見せることがあるのです。
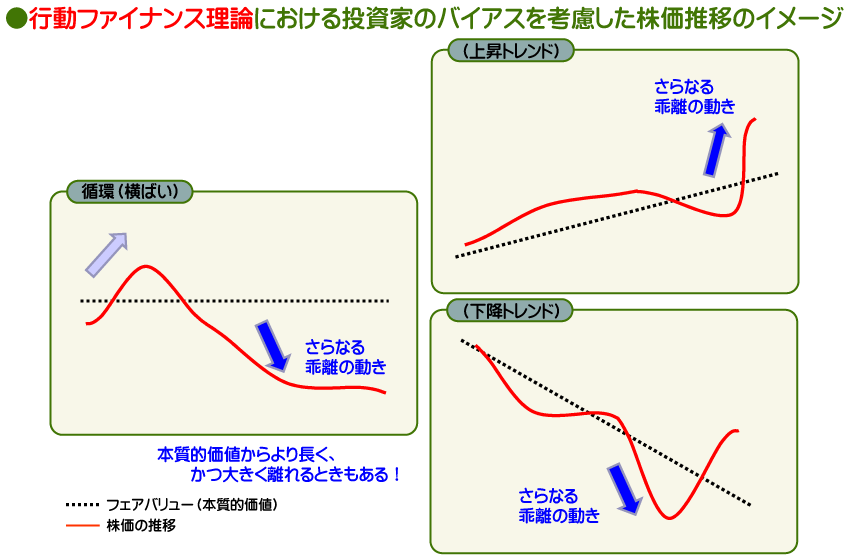
市場がファンダメンタルズ分析だけによらない値動きを見せることを知っていれば、それを踏まえた上で適切な投資行動を取ることが可能になります。と同時に、自分自身がこうしたバイアスによって失敗していないかどうか、客観視することも重要です。客観視した上で、それをどのように行動に結び付ければよいかという行動コーチングについては、後ほど改めて説明します。
■中長期の資産形成でもテクニカル分析を活用する意味はある
テクニカル分析というと、株式の短期的な売買などに使うものと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、投資信託による中長期投資でもテクニカル分析を活用すべき局面は大いにあります。
そもそも、テクニカル分析は、株価などのデータを分析して相場の先行きなどを予測する手法です。株価形成は、人の行動や価値観、心理学などを反映したすべての市場参加者の集合的な結果であるという考え方がベースになるので、ファンダメンタルズ分析では対応できない、市場の非効率な動きや投資家の不合理な行動についても一定の対応が可能になると考えられています。また最近では、AIやフィンテック、データサイエンスといった新しい分野との融合も進んでいます。
テクニカル分析には、移動平均乖離率、ゴールデンクロス・デッドクロス、ボリンジャーバンド、RSI、騰落レシオ、サイコロジカルライン、フィボナッチ・リトレースメントなどさまざまなものがありますが、ここではわかりやすい例として移動平均乖離率の活用法を紹介しましょう。
移動平均乖離率は、ご存じのとおり、実際の値動きと移動平均線との乖離から投資タイミングを計る指標で、中長期が前提であれば、移動平均線は200日(=約半年)など長めのものを使用します。たとえば、日経平均であれば20~30%以上なら買われ過ぎ、逆に-20~-30%を下回れば売られ過ぎと言われています。これを頭に入れておくだけでも、上昇時の高値づかみや暴落時の狼狽売りのリスクを減らすことが可能になります。
もちろん、それぞれの投資信託が投資する対象によって見るべきチャートは変わってきます。日本株が中心の投資信託なら日経平均株価ですが、たとえば米国株や先進国株式に投資する商品であればS&P500やNYダウなどの200日移動平均乖離率をチェックしましょう。なお、対象が変わると過熱感や割安感を示す数値もそれぞれ変わってくるので、その点は注意が必要です。
■今後は、顧客を合理的な投資行動へと促す「行動コーチング」が普及する
さて、投資家が陥りがちなバイアスについての知識があり、投資で自分がどんな失敗をしがちなのかが理解できても、実際の行動を変えられなければ意味がありません。そこで注目されているのが、冒頭でも少しお話した投資に関する「行動コーチング」です。行動コーチングの先進国である米国では、すでにFP(ファイナンシャル・プランナー)が提供するサービスとして、アセット・アロケーションやリバランスなどと共に、顧客の投資行動を合理的なほうへと誘導する「行動コーチング」が挙げられるようになってきています。
たとえば、市場が大きく下落して怖いから持っている投資信託をすべて売りたいという顧客がいたときに、行動コーチングでは「リーマン・ショックのときはどんな行動を取りましたか? 当時と比べて恐怖の度合いはどうですか?」などと対話をしていきます。こうした対話を通じて、FPは顧客にバイアスに影響された行動を取っていないか気づかせて、顧客が合理的な投資行動ができるように促していくのです。
その際には、先ほど説明した移動平均乖離率などのテクニカル分析も役立ちます。「歴史的に見ても、今は非常に割安な水準で売られ過ぎの状態です。ここは売ってしまうのではなく怖くても持ち切りましょう」とデータを示すことで、市場変動の波に振らされずに冷静な投資行動を引き出すアドバイスが可能になります。
コーチング自体は以前からありましたが、臨床心理学も取り入れた投資分野での行動コーチングというのは、ここ数年の新しいトレンドです。金融業界で顧客本位の対応が求められる中、今後は一般的になっていくと考えられます。ただし、米国に比べると日本ではまだまだ知られているとは言えません。ようやく金融庁の勉強会などで取り上げられるようになったところで、これから投資のプロが取り入れて、その後、個人の投資家にも広く知られるようになる流れではないでしょうか。
■積立投資でも、行動ファイナンスとテクニカル指標は意識してほしい
最後に、投資信託を積立で購入している人に向けて、少しアドバイスをしたいと思います。積立投資の場合、緩やかな下落相場であれば冷静に対処できる人がほとんどです。つまり、慌てて売らずに、淡々と積立を続けていくことができます。ただ、5年、10年という長いスパンの中では、リーマン・ショックのような大きな変動の波も訪れます。そうなると、積み立てて来た資産が20~30%以上も下落する場合があり、「本当に戻るのか」「怖くてこれ以上持っていられない」と、積立を断念して売却してしまう人が少なくありません。
しかし、そういうときこそ今回お話しした「行動ファイナンスにおけるバイアス」と「中長期のテクニカル指標」を思い出して、冷静な投資行動を取ってほしいと思います。また、積み立てている資産が大きく値上がりしたときには、「積立だからほったらかしにしていい」という思い込み、決めつけるのではなく、やはりテクニカル指標なども参考に、高くなっている資産を他の資産に振り替えるといったリバランスを検討することも重要です。そうすれば、仮にその後大きく下落することがあっても、精神的にも余裕を持つことができます。
せっかく投資信託で中長期の資産形成をしようとしているのに、投資を続けるべきタイミングで投げ売りしてしまったり、逆に高値圏にあるときにも「何もしなくていい」と決めつけてしまったりを繰り返していては、資産形成はなかなか進みません。ぜひ「行動ファイナンス」と「テクニカル指標」を意識した行動を取って、中長期でのパフォーマンスの向上に結び付けてほしいと願っています。
中村貴司(なかむら・たかし)
東海東京調査センター シニアストラテジスト
日系・外資系証券会社、損保・証券系運用会社でアナリストや年金基金、投資信託のファンドマネージャー等を経て、現職で日本株・リート・ETFを含むテクニカル分析などに従事。伝統的ファイナンス理論を中心としたファンダメンタルズ分析に加え、投資家心理・投資家行動を中心とした行動ファイナンス理論やテクニカル分析などをテーマにした講演多数。日経CNBC等のTV・メディアに出演。東洋経済オンラインやロイターなどでも執筆、コメントを行う。世界のテクニカルアナリスト協会を束ねる国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の理事などを歴任し、早稲田大学ビジネスファイナンスセンター「ファンドマネジメント講座」や同志社大学等で講師も務めている。顧客本位のスタイルを重視し、実践で活用できる投資・金融経済教育の普及・啓発や中立的な提案・アドバイスを重視している。



